平家山(1496.5m)〜後平家山(1560m)〜南平家山(1510.2m) 熊本県 |
|||
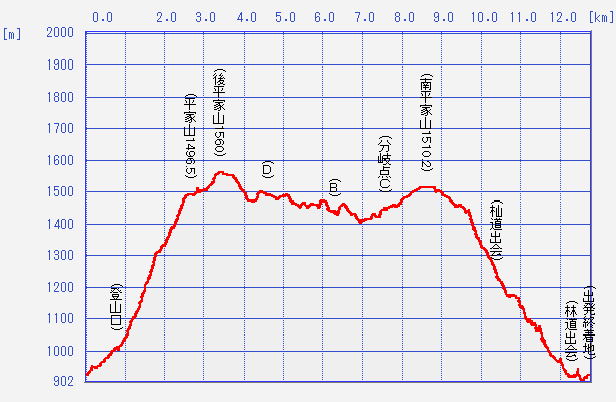 1 経路概念図 クリックで拡大 |
 2 林道、舗装の終点 ここから歩き始める。林道は未舗装になり前方奥へ続いている。 |
2009年9月18日 八代市泉町葉木腰越から北東に林道葉木線が延びている。その林道沿いにある平家山登山口から、標記3座を経て「とぞの谷橋」へ周回した。 距離は13.2km、所要時間は8:30であった。 この日の計画は、平家山の先からまだ歩いていないルートを五家宮岳へ向かう予定である。 五家宮岳へは、2008年12月に下屋敷側から登っているが、今回のルートを歩き通すことができれば、目標にしていた五家荘の全ピークと全ルートを歩き終わることになる。 しかし、このルートの事前情報はほとんどなく、早朝から正午まで進んでみて、五家宮岳まで到達できなければ、そこから引き返す心づもりである。 幸いなことに、先日お会いした熊本県の山に詳しい方から「五家宮岳北東の尾根筋から北西へ下るルートをがあり、分岐点は分かりやすいように刈り払っている」との情報を得ていたので、この分岐点を発見できれば、それを下ることも想定して出発する。 車は、林道の舗装が終わる所に駐車して出発する。 林道はその先100mほどの所で、のり面の上下が崩落しているが歩くのに支障はない。 歩き始めて15分、800mほどで写真3の登山口に着く。 登山口から踏み跡に沿って下り、渓流を渡る。対岸の山腹を巻くように進み、砂防堤の先で再び沢を渡る。 そこからは、スギ林の中をジグザグに登り尾根に出る。しばらく登ると、杣道が左に分岐し(写真7)、その先10mで右に分岐する。(写真8) 杣道の分岐点から600mほどのところで「スズメバチ注意」のメモ紙を見つけた。そのすぐ先で、自然木の株元にできたウロからキイロスズメバチが出入りしている。 巣がある自然木は登山道の横30cmほどのところ。 スズメバチの動きを観察しながら、ゆっくり近づいてみる。このときは早朝で気温が低く、彼らの活動は低調のようだ。静かに見ていると、警戒態勢をとることもないので、そーっと近寄り、素早く通り過ぎた。 しばらく登ると、京丈山と平家山から国見岳を結ぶ縦走路に出会う。そこには、五家荘登山道整備プロジェクト皆さんが、今年5月に立てた分かりやすい道標がある。(写真11) 縦走路に出会ったすぐ先が平家山の山頂である。(写真12.13.14)山頂は樹林の中で眺望はない。 一息入れて、国見岳への縦走路を進み、五家宮岳へ連なる尾根の分岐点を目指す。 縦走路は心地よい自然林である。平家山の山頂から600mほどのところに道標がある。(写真16) 道標の右端から、北東方向へ薄い踏み跡らしいものがついていおり、地図とコンパスそれにGPSで現在位置と進行方向を確認する。 ここで縦走路と分かれ、五家宮岳方向へ延びる尾根に入る。 踏み跡らしいものはすぐに消え、灌木やスズタケの中を進む。しばらく進むと「後平家山」の標識(写真19)に出会う。今回はルートの事前情報がほとんどなく、この鈍頂に名前があることも知らなかった。 この山頂標識は思わぬプレゼント。これで、登った山が一つ増えた。 後平家山からは目印が現れ、幅の狭い切り分けもある。スズタケは枯れかけていて、予想以上に歩きやすい しばらく進むと、元気なスズタケが登山道を覆うが、薄いながらも踏み跡は続いており、古い切り分けの跡もある。 尾根筋のルートをはずさないように注意をしながら進んでいたが、地図のD地点(写真23)で進行方向を間違えた。原因は、うっかりの直進である。しばらく進んで、地形の状況から間違いに気づき、間違った地点もすぐに想像できた。 この間違って進んだ部分には、スズタケを折ったルートサインが続いているので注意が必要だ.. D地点まで引き返し、五家宮岳方向へ進む。スズタケはだんだん濃くなり、倒木があるところはヤブの中を大きく迂回しながら進む。 B地点で、地図に記載されている北西へ延びる破線の道を探してみるが、見つけることはできない。 スズタケの尾根をなおも進むと、地図の分岐点Cで道標と目印(写真29,30)を見つけた。道標は、出発地点の近くにある「とぞの谷橋」へのルートを示している。時刻は11時25分。 地図を見ると、当初計画をしていた五家宮岳まではかなりの距離があり、五家宮岳まで行って日没前に出発地まで帰り着くのは困難である。 ここで予定を変更し、五家宮岳までの残りのルートは次の機会に歩くことにして、900m先の1510.2mピークまで行くことにする。 その後は分岐点Cまで戻って「とぞの橋」へ下ることにする。 五家宮岳への登山道の状況確認を兼ねて尾根を進む。踏み跡と目印は続いているが、スズタケは益々濃くなって登山道を覆う。 自然林が途切れたところからは、東に主峰の国見岳が見える。(写真25) 1510.2mピークの下まで進むと、山頂へ向かって明瞭な踏み分け がある。その踏み分けを辿ると数分で小さな広場に出た。(写真26、27、28) そこには三角点があり、立木には「南平家山」の標識もある。このピークに名前があることを知らなかったので、二つ目の嬉しいプレゼントい ただいた気分である。ちなみに、この三角点の点名は「桜谷」である。 「南平家山」の山頂からは、目印が北西方向へ続いているようであり、地図の破線の道に沿た登山道があるのかも知れない。 先ほどの五家宮岳へ通じる登山道まで引き返し、五家宮岳の方向をうかがうと、踏み跡は続いているようである。 次の機会にはこの先を歩くことにして、分岐点Cへ引き返す。 分岐点Cからは、狭い切り分けと踏み跡が続いており、目印もある。踏み跡は尾根に沿って下り、やがてスギ林の中を下る。 しばらく下ると、左右に通る杣道に出会う。(写真32)目印はここまでで終わり、道標もない。 地図で凡その検討をつけ、杣道を右、北方向に下る。 杣道は明瞭で歩ききやすい。スギには所々にテープが巻かれているが、林業の目印のようだ。 杣道は谷沿いに下り、幅の広い作業道に出る。作業道は間もなく終わり、また狭い杣道になる。 途中には古い丸太の橋が数カ所あり、安全を確認しながら渡る。(写真33) 杣道はやがて林道に出会う。(写真36)この林道を進行方向とは逆に30mほど登ると、「作業道桜谷線」と書かれた石碑が建っている。 林道の出会地点から100mほど下ると、林道葉木線の「とぞの谷橋」に出る。(写真38)「とぞの谷橋」から出発地点までは僅か200mほどであった。 通過時刻(GPSデータ) 出発 6:20 平家山 8:02 後平家山 8:31 分岐点C 11:24 南平家山 12:14〜12:44 分岐点C 13:20 杣道出会 13:56 終着地 14:50 |
|
 3 林道は出発地のすぐ先で崩壊 |
 4 登山口近くの林道 |
||
 5 林道沿いの平家山登山口 |
 6 二つ目の渡渉点 |
||
 7 尾根の杣道分岐点 |
 8, 7の10m先で、再び杣道が分岐 |
||
 9 平家山へ向かう尾根上の登山道 |
 10 スズタケのトンネル |
||
 11 縦走路出会いにある道標 五家荘登山道整備プロジェクトの皆さんが今年5月に設置 |
 12 平家山山頂 |
||
 13 平家山の山頂標識 |
 14 平家山の三角点 |
||
 15 平家山から国見岳への縦走路 |
 16 分岐点Aにある平家山と国見岳方 向を示す道標 |
||
 17,16の道標付近 ここで縦走路と分かれ、裏平家山方向へ向かう |
 18 シイタケによく似たツキヨタケ (注意) |
 19 後平家山の山頂標識 下には八代ドッペル登高会の表示 |
 20 スズタケが枯れた南平家山への稜線 この先で、またスズタケが登山道を覆う |
 21 南平家山への稜線にある目印 目印の間隔は遠い。 |
 22 カエデの一部の枝で始まった紅葉 |
 23 D地点の広場 ここで進行方向を間違 え、直進をしてしまった |
 24 見事なブナの大木 |
 25 稜線から見る国見岳 |
 26 南平家山山頂 |
 27 南平家山の山頂標識 |
 28 南平家山の三角点 |
 29 分岐点Cの道標 ここから「とぞの谷橋」へ下る。 |
 30 分岐点Cから杣道出会まで続く目印 |
 31 美しい自然林 |
 32 杣道出会 右、北方向へ下る |
 33 杣道に架かる古い丸太橋 |
 34 林道出会いから林道を30mほ ど 登った所にある林道(作業道桜谷 線)開通 記念碑 |
 35 ゲンノショウコ |
 36 杣道から林道(作業道桜谷線)に出たところ |
 37 38の右端に立っている標柱 |
 38 とぞの谷橋の周辺 手前下方向が腰越 |
 39 出発地のそばに咲いていたジキタリス |
 Back |