ウードヤ山(1355.7m)〜五家宮岳(1538m) 熊本県 |
|||||
経路概念図 クリックで拡大 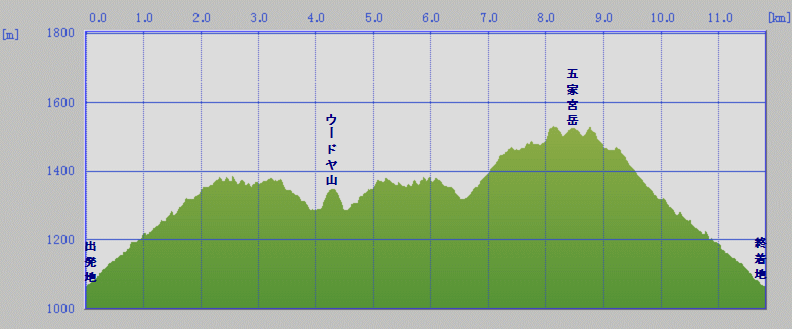 |
 ウードヤ山々頂の三角点 |
 管理道支線の上に、こんもりとした姿を見せるウードヤ山 |
|||
 出発・終着地 ここから右へ管理道支線を歩く |
2008年12月1日 八代市泉町の五家荘を通る国道455号線から、下屋敷で林道下屋敷樅木線が分岐をしている。その林道の分岐点から約500mほどの所で、さらに県所管の保安林管理道が北方向へ分岐している。 今回は、その管理道を車で進み、途中から分岐している支線を歩いて二つの山を往復した。距離は12.2km、所要時間は7:24であた。 今回は山に詳しい民宿に泊めていただき、山や登山道の状況を丁寧に教えていただいた。目的の山はウードヤ山であるが、天気が良くて時間にも余裕ができれば、北に位置する五家宮岳にも登る計画である。 民宿のご主人の話では、ウードヤ山への登山道は2本あり、一つは樅木から、もう一つは今回歩いた下屋敷から分岐している管理道を利用するルートである。 樅木からのルートはスズタケが茂っていて歩きにくく、おすすめは管理道を利用するルートとのこと。しかし、この管理道は先の方で工事が行われていて、下屋敷の入り口はゲートが設けられ、通常は施錠されている。 今回は目的が登山ということで、民宿の取り計らいにより、管理道を通していただいた。 管理道の主線は一車線であるが、舗装がされていて車は快適に通行できる。しばらく進むと支線が分岐しているが、この最初の支線分岐点Aは見送り、管理道の入り口から3.1kmほどのところで、次の支線が分岐している。 この支線分岐点Bには広い土捨て場があり、工事の邪魔にならないところに駐車をして、支線分岐点Bから歩くことにする。 この支線は、ススキが茂っているところや少々荒れているところもあって、車での進入は不可能である。 歩き始めると、前方に五家宮岳の姿が見えてくる。帰りに登る予定もあって、手頃な取り付き地点はないかと、探しながら進む。しばらく進むと、支線は傾斜が緩やかな人工林の尾根を横切る。注意深く観察すると、人工林は稜線の近くまで延びているようだ。帰りに、この支線から五家宮岳を目指すとすれば、ほど良い取り付き地点のようである。 この位置をGPSに記録して、先へ進む。支線は、山襞に沿って曲がりながら、緩やかに登っている。稜線に近づくと視界が一気に開け、五家荘の大パノラマが目に飛び込んでくる。 北には京丈山、西には保口岳そして南には雪の上福根山が見える。雄大な山岳展望を楽しみながら進むと、「ブナの里帰り」の看板に出会う。この看板は、伐採で傷んだ森を再生させる取り組みを知らせるもののようだ。 稜線のすぐ下を通る支線が下り始めると、先の方にこんもりとした小さなピークが見えてくる。地形図とコンパスで確認をすると、目当てのウードヤ山である。 支線を下りながら取り付き地点を探すが、一帯は濃いスズタケの藪である。さらに支線を下ってウードヤ山の南西側に達すると、支線はウードヤ山から南西に延びる尾根の中心に近づく。今回はこの地点に目印の赤テープを付けた。 尾根の中心に登って踏み跡を探すと、かすかな痕跡が山頂方向へ続いている。この痕跡は、樅木からの登山道であろう。登山道の大部分はスズタケと自然木の藪であるが、背丈の高い立木は切り倒されていて山頂を視界に入れながら進む。 ほどなくして、山頂に到達する。山頂にはテレビの中継アンテナが立っていたらしく、 今は廃棄された資材が倒されて置いてある。山頂に標識はないが、三角点の周辺には遮るものがなく、すぐに見つけることができた。 山頂からの展望は素晴らしく、脊梁の山々が幾重のも重なり連なっている。遠くの山の中腹には人家も見え煙が立ちのぼっている。この風景を眺めていると、山深い五家荘に暮らす人々のぬくもりが伝わってくるようである。 歩き始めてから山頂まで、先ほど付けた目印以外に、目印や道標は全くない。ウードヤ山への到達は順調で、日暮れまでの時間には余裕ができた。 そこで、当初に予定をしていた五家宮岳へ向かうことにする。ルートはウードヤ山から続く稜線上にある。しかし、民宿のご主人の話では、稜線はスズタケの藪が濃いようなので、往路で見つけていた取り付き地点まで支線を戻ることにする。 支線の取り付き地点からは、人工林と自然林の藪の境目を稜線へ向かって登る。踏み跡や目印はないが、人工林の枝の下は灌木もなくて歩きやすい。地面には雪が現れ始め、しばらく進むと人工林が終わる。 そこからは、背丈を超えるスズタケの藪である。地形図を見ると稜線までは近く、意を決して濃い藪をかき分けながら進む。ほどなく、稜線の少し手前で左右に延びる薄い踏み分けに出会う。この踏み分けはウードヤ山から続く縦走路のようだ。 その踏み分けを北東へ進む。踏み分けは薄くスズタケが覆っている。踏み分けには、間隔は遠いが古い目印が点々と付いている。積雪は徐々に多くなり、雪の重みでスズタケが左右から登山道に倒れ込み、踏分を見つけるのが難しい。倒れたスズタケの上の雪を落とし、スズタケを立ち上がらせてから、踏み分けを探しながら進む。 地形図のD地点まで進むと、踏分らしいものは目の前の小ピークを巻くように山腹へ向かっている。おかしい、と思ったが、たぶん巻き道であろうと思って、歩きやすい藪の隙間を進む。隙間はだんだん狭くなり、地形図のE地点でなくなった。 引き返して、稜線に続いているであろう踏み分けを探す事も考えた。しかし、地形図で確認すると、稜線までの距離は長くはないようであり、稜線へ向かって直登をすることにする。急坂の濃いスズタケの藪の中を、前進後退、右往左往しながら進む。濃い藪をかき分けながらの登りは、思った以上に体力を消耗する。 しばらくして稜線に出たが踏分は見つからず、稜線を右に左に移動しながら進んでいると、古い目印を見つけた。そこからはまた、雪で倒れたスズタケを起こしながら踏分を探して進む。ほどなくして、五家宮岳の手前のピークに到達する。そこは、スポット状にスズタケがない直径2mほどの空き地で、雪の上に腰をおろして昼食にする。 そのピークから下り、鞍部で地形図のG地点を通る破線の道を探すが、見つけることができない。もし見つけることができれば、復路はその破線の道を下る計画であった。 鞍部からは、一登りで五家宮岳の山頂である。山頂は立木の中で眺望はないが、古い立派な標識ある。 山頂からは往路を引き返す。往路のミスコースで稜線に復帰したF地点からは、稜 線の中央を歩いてDに出会う。 Dからは往路を忠実に辿り、取り付き地点を経て支線の分岐地点へ戻った。 通過時刻(GPSのデータより) 出発 7:54 ウードヤ山 10:14 地図C地点五家宮岳とりつき 11:36 地図E地点 12:15 地図F地点 12:25 地図G地点 12:52 地図H地点 13:11〜31 五家宮岳 13:51 五家宮岳とりつき 14:40 終着地 15:18 |
||||
 管理道支線から見た京丈山方面 |
|||||
 五家宮岳 |
|||||
 五家宮岳山頂 |
 稜線に積もる雪 |
||||
 五家宮岳への稜線 雪の重みで登山道に 倒れ込んだ背丈を超えるスズタケ |
|||||
 管理道支線に連なるつらら |
|||||
 霜の降りた管理道支線 |
|||||
 管理道支線の霜柱 気温はマイナス2℃ |
 管理道支線の水たまりに出来た氷 |
 落ち葉にできた霜の結晶 |
|||
 Back |
|||||