茶臼山(1446m) 熊本県 |
|||
経路概念図 クリックで拡大 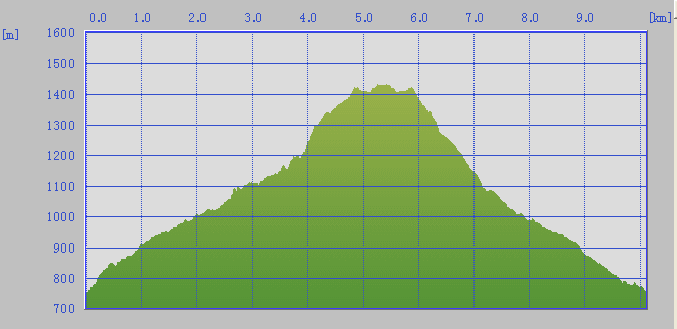 |
12月9日 八代市泉町五家荘の一つである久連子から山頂を往復した。距離は10.5km、所要時間は往路3:45、昼食0:30、復路1:40、合計5:55であった。 事前に登山道の情報を得ることができずに入山をしたため、往路では地図読みやルートの維持、藪の中の通過に多くの時間を要した。 往路で復路と同じルートを歩いていれば所要時間は1:00〜1:30程度の短縮ができたものと思われる。 入山地点は市役所から丁寧に教えていただいた。登山道については詳しいことは分からなかったが、山頂へのルートはあるとのことであり、地形図から登山道のおよその位置を推定して入山することにした。 登山道が通っていると推定しているのは地形図の1262mピークからD地点辺りの稜線である。途中で登山道が分かれば登山道を進むが、分からなければできるだけ林道や作業道を辿って山頂へ近づく計画だ。 途中で濃い藪や危険な岩場などに出会い、進むのが困難になれば無理をせずに引き返す考えである。今回は、私たちにとってはかなりの冒険になりそうである。冒険とは無事に帰り着くこと。気分を引き締めて出発する。 登山道の取り付きは、林道久連子椎原線の日当橋から約1.9km地点である(地形図:出発終着地)。目印や特徴のある物は何もない。山側の法面に作業道がつけられていて、そこから歩きはじめる。法面を登り上がると自然林となり、踏み跡は全く分からない。新しく積もった落ち葉の下になっているのだろうか。 見当をつけてしばらく進むと杣道に出た。地形図にに載っている「岳」へ通じる破線の道のようだ。杣道を北東へ進むと林道へ出た(林道出会)。そこには民家があるが、今は人が住んでいないようである。 林道を道なりに進むと「殿屋敷跡」の真新しい標柱に出合う。日当たりが良く、住むのには良さそうな所だ。平家の名のある人の屋敷跡であろう。 平家の歴史に思いを巡らせながら林道を進んでいると三叉路に出合った。ここは分岐を北々西へ進み、やがて林道の終点(B)に着く。 下山時に気づいたが、BからはCへ向かう踏み跡があるものと思われるが、確認はしていない。 私たちは林道の終点BからCへ向かう道には気づかず、終点から北へ延びている幅2mほどの作業道を進む。作業道はやがて終わり、踏み跡を辿るがしばらくすると踏み跡も終わって道はなくなる。やがて谷に出合うが、岩が累積をする急傾斜の谷を遡るのは危険であり、手前の尾根を東へ進む。 この辺りは獣道が縦横に走っていて、進行方向に沿った歩きやすい獣道を利用しながら急な尾根を登る。F地点の少し手前からスズタケの藪になりFとEの中間辺りで岩場となる。安全に通り抜けられそうなルートを探して慎重に進む。 上空を見上げると、タカが一羽、青空の中を悠然と旋回している。 岩場を抜けると、背丈を超えるスズタケの藪は一段と濃くなり、見通しは数メートル。それに倒木も重なっていて、スズタケをかき分けながら、倒木を乗り越え、くぐり、迂回をして進むのは体力を消耗する。 やがて傾斜が緩やかになり、稜線に乗り始めたことを知る。ここまでに要した時間は3時間近く。 この辺りで登山道を見つけることができなくて、濃い藪が続くようであれば引き返すことも考えながら、GPSの地図画面を見ると山頂までは400mほどである。GPSの画面は小さいが、等高線の中に「茶臼山」の文字が映し出されている。 気を取り直して注意深く藪をかき分けながら進んでいると、かすかな踏み跡に出合った。うっかりすると、見落として横切りそうな踏み跡である。踏み跡は稜線上を南西から北東方向へ続いている。この踏み跡は私たちが想定をしていた登山道のようだ。 慎重に辺りを探すと古いテープの目印もあり、登山道であることを確信する。引き返さずに済んだ。ほっとして嬉しくなり、重かった足取りが急に軽くなる。 頭上を覆う藪の中を数十メートル進むと急に明るくなり、視界が一気に広がった。切り払われた所に出た。 見渡すと、上福根山から茶臼山へ続く稜線がすぐ近くに見え、東には南山犬切、南には先日歩いた鷹の巣山から蕨野山、積岩山への稜線が連なっている。 ここからは登山道も明瞭で快適だ。やがて、上福根山から茶臼山へ連なる稜線に合流して、北西へ進む。稜線の登山道は切り分けられていて、歩くのに支障はない。緩やかな稜線をしばらく進み、小高くなったところを一登りすると山頂である。 山頂は切り開かれていて、三角点のそばに山名標識が立てられている。山頂からは自然林の枝越に、国見岳から烏帽子岳への稜線や九州の脊梁のなす山並みが、幾重にも重なり連なっている。 復路は登山道をEまで戻り、そこからはD〜Cを経て往路で通った林道へ出た。山頂から林道までの踏み跡は、E付近を除いてほぼ明瞭である。 途中、Dの所でシカよけネットに出合い、その先は道なりにスギ林の中を下る。C地点まで下ると、この日唯一の道標「茶臼山上福根山 林道を往路で出合った「林道出会」地点へ。そこからは林道をそのまま下り、Aの林道久連子椎原線に出て、出発地点へ戻った。 今回のルートを歩いてみて、入山地点としてはAがわかりやすく、登山道はA〜B〜C〜D〜E〜山頂であろうと思われる。 私たちが往路で歩いた、Bの林道終点からFを経てEへ至るルートは、途中からは道がなくなり、藪が濃くて岩場もあることから避けた方がよい。 |
||
 茶臼山 |
|||
 山頂 |
|||
 上福根山から続く稜線上の登山道 |
|||
 「殿屋敷跡の標柱」 |
 ブナにつけられた ペンキの目印 |
||
 よく目立つイイギリの実 |
 地形図C地点の道標 |
 ソーセージのような ツチアケビ |
|
Back |
|||