カラ迫岳(1006m) 福岡県
山頂から360°の眺め
経路概念図 クリックで 拡大
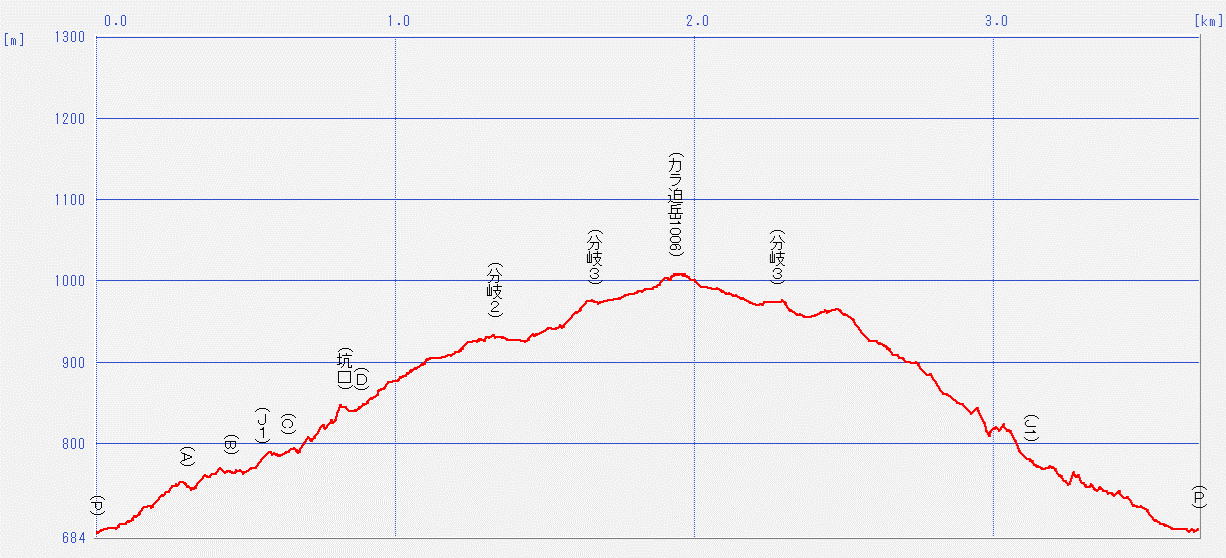
山頂
2015年5月21日
一昨日に続いてカラ迫岳へ。目的は、地図の分岐3からJ1へ通じるルートの調査である。
登山道沿に沿う渓谷の水は大きく減少して1/5ほどに。
心地よい水音とオオルリの声を聞きながら、自然林の中を登る。下山時に合流する分岐J1の位置⑪を確認して、分岐2のT字路⑥に到着。
T字路の少し手前からは、南東方向に石割岳が大きく見える。T字路を左へとり、国境石を見ながら進むと分岐3、⑦に着く。帰りは、ここから西方向へ延びる周回路を下る予定である。
山頂は一昨日に比べてやや霞んでいるもの、遠くには時折吹き上がる阿蘇の噴煙が見える。
ふと上空を見ると、遠くにクマタカの姿。クマタカは、初夏の風に乗って悠然と舞ながら遠くへ去った。
山頂から分岐3へ引き返して、J1へのルートを下る。ルートはカシやシイ、それにヤマザクラなどの素晴らしい自然林が続く⑩。
やがてJ1に出会い、そこからは往路を引き返した。
今回のルートは、良く保全されており、道標もあって分かりやすい。ただ、J1には下ってきたルートを示す道標は見当たらなかった。
下山後に、八女市役所星野支所に立ち寄り、カラ迫岳の登山のことについて、多くのことを教えてていただいた。
そして、地域興しの中で登山道の整備を続けられている組織、「上郷村」のお世話役Aさんを紹介してもらった。
その足でAさんにお会いして、登山道整備の思いたちや毎年行われている山開きなどの諸行事、それに今後の展望などを伺った。
Aさんによれば、この日に歩いたカラ迫岳の周回ルートは、多くの登山者の方々に歩いていただきたいとの願いを込めて、保全を続けているそうである。
山頂から見る右から御前岳、釈迦岳、普賢岳
中央奥は阿蘇の噴煙
小さな爆発でも繰り返しているのであろうか、間欠的に立ち上る噴煙
遠く高いところを舞うクマタカ
タツナミソウ
①
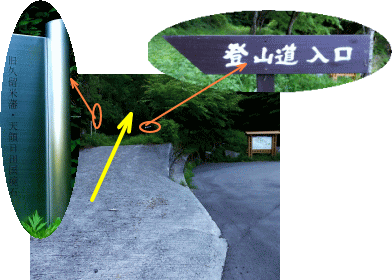
登山口
左に国境石群の解説板
登山口の近く
空を覆う、すがすがしい新緑
②

③
流れを3回渡る
④

金坑跡の縦穴
ミズタビラコ
⑤
金坑跡の横穴
⑥

分岐2のT字路
左へ進む
ヤマキツネノボタン
⑦

分岐3 周回路の分岐点
黄色の矢印は往路の山頂方向
青の矢印は下山路のJ1方向
⑧
国境石
ノバラ
⑨

山頂のすぐ手前にある、熊渡
山へ通じる縦走路標識の標識
⑩
分岐3からの下山路
素晴らし自然林が続く
分岐3からの周回下山路にある横穴
金坑の跡であろうか
⑪

地図のJ1 下山時の往路との合流地点
青色の矢印は復路の登山口方向
黄色の矢印は往路の山頂方向
「登り道」の道標は黄色の矢印の先、谷側にある
分岐2付近から見る、右の石割岳と左は平野岳
ガクウツギ
マルバフユイチゴ
タニギキョウ
ナルコユリ
ツクバネソウ
フタリシズカ
ツクバネウツギ
ヤマツツジ
ギンリョウソウ
キンチャクアオイ
カンアオイ
サトキマダラヒカゲ

Back